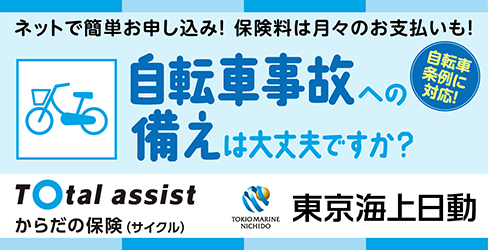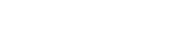法人賠償保険のスペシャリストです
CREATEは中小企業を「正確・最適・安心・あったらいいな」のサービスで応援する会社です。特に法人向け賠償保険に特化しています。
ご契約いただいているポートフォリオも法人が99%と数字からも法人に特化していることがわかります。さらにそのうち実に64%が賠償ラインとなっております。
ここではCREATEがなぜ法人の賠償保険に特化しているのかをご紹介させていただきます。
1. なぜ賠償保険に特化しているのか
特に中小企業の経営における「賠償リスク」は、発生頻度は低くても、一度起きれば企業に甚大な損害を与えかねません。
高額な損害賠償金は財務状況を逼迫させるリスクをはらみます。
もちろん金額だけでなく、関わるステークホルダー(取引先や社会)からの信頼を失うことも稀ではありません。
報道やSNSによる風評リスクは長年の歴史ある、その業種または日本経済を支えてきた大企業でさえも致命的なダメージを与えることもあります。
そして何よりもこの中小企業への財務・風評といったダメージによって危機に晒されるのは、そこで働く従業員の皆様であり、その先にはそれぞれの従業員の家族の生活も繋がっていることは言うまでもありません。
だからこそ私たちCREATEは、そうした「経営そのものを揺るがすリスク」から企業を守るため、賠償保険のスペシャリストになる道を選びました。
高度な専門保険知識をもとに、複雑な保険制度をわかりやすく噛み砕き、日本の中小企業の経営者の皆さまを支えています。
2. 賠償事故が企業に与える影響とは
前述のとおり、賠償事故は、単なる損害賠償金による財務逼迫による事業資金の枯渇という側面だけにとどまりません。
法人の経営者の皆様のご相談で多いのはやはり「明日の売上」と「人材」です。
ただでさえ働き手市場の中、特に建設業・ビルメンテナンス管理業・製造業といった日本の屋台骨を支える企業では人と時間・お金を投資して募集をかけてもなかなか人が集まらず、やっと採用ができても定着しないという課題を良くお伺いします。
その中でやっと集まった社員などが、様々な賠償、例えば不当解雇やハラスメント、企業の販売した商品による人的被害、作業中による第三者の財物損壊、情報漏洩や労災訴訟といったもので会社名が取り上げられれば、好奇の目にさらされモチベーションが低下したり、企業への信頼度も揺らぐこととなります。
さらに事故を起こした企業としての社会的イメージ低下、SNSや報道により風評被害が拡大すれば、おのずと顧客離れや信用収縮による売上減少へと繋がっていきます。
万が一の事故が社員のモチベーション・雇用継続に影響を与え「企業の命運」を左右することも珍しくありません。
3. 賠償責任の基本とは?
企業が日々の業務で背負う可能性のある「賠償責任」には、主に次の2種類があります。
これは、事故やトラブルが起きたときに「どの法律に基づいて責任を問われるか」に関わる、大切な考え方です。
【1】不法行為責任(民法709条)
相手と契約がない場合でも、過失や不注意により他人に損害を与えたときに生じる責任です。
たとえば、通行人や来訪者などに対して起きた事故はこちらに該当します。
工事現場で工具が落下し、通行人に怪我を負わせた、清掃中に床が滑り、訪問者が転倒して骨折したなど様々なケースが考えられます。
【2】債務不履行責任(民法415条)
こちらは、契約を結んでいる相手に対し、契約どおりの義務を果たさなかったときに問われる責任です。
工期を大幅に遅延し、顧客が営業損失を被った、契約内容と異なる資材を使用していたことが後に発覚した、品質不良などが典型例です。
賠償責任は、経営リスクそのもの
これらの責任は、いずれも裁判や示談に発展しやすく、企業にとっては金銭的負担だけでなく、信用・雇用への波及リスクを伴います。
特に中小企業にとっては、「たった一度の事故」が経営を揺るがす事態になりかねません。
これらは企業活動において避けがたいリスクであり、法的責任を回避する手段として賠償保険の役割が極めて重要です。
4. 主な賠償リスクとその概要
次に実際に弊社で対応した事故例をもとにどのような保険種類が対応し、またどのような関連法案のもとに賠償請求されたかを一部ご紹介いたします。
①第三者賠償
建設・ビルメンテナンス・製造・運送業などを中心に多くの企業が抱えるリスク。
業務遂行中や施設内における賠償補償と、引き渡し後や生産物(PL)賠償補償が主な補償となります。
企業の過失によって、業務とは関係ない第三者や第三者の財物を損害したことによる、企業が負う法律上の損害賠償額を補償します。
該当する法的責任
不法行為責任(民法709条)
具体的な事故例1
工事中の足場部材が落下し、通行人が頭部負傷。くも膜下出血により入院とリハビリを要す。
→治療費・仕事を休んでいる間の休業補償・慰謝料により2,650万円の損害賠償請求発生。
具体的な事故例2
工事中に重機同士を接触させてしまい重油が近隣建物に飛散。近隣マンション居住者30名の車、マンション外壁、幼稚園外壁を汚損。
→居住者30名と免責証書(示談書)を交わすまで約2か月を要し、損害の総額は2,700万円
具体的な事故例3
食品を販売後、食品に金属破片が混入していたため、口にした女性が怪我。また同日生産された食品400個を自主回収することになった。
→治療費・休業補償・慰謝料、自主回収費用で400万円の損害
②雇用慣行賠償
企業の雇用に関して、不当解雇や各種ハラスメントにより従業員から直接、または労働審判やユニオンなどを通して損害賠償請求された際の補償。
雇用関連トラブルの場合は従業員との労使交渉はもちろん、それ以外の思わぬ企業への風評ダメージ(会社前での拡声器などによるスピーチ、SNS発信など)による、在職従業員のモチベーション低下などもリスクとなり、思わぬ甚大な経営的損害が発生します。
該当する法的責任
債務不履行責任(民法415条)、労働契約法(使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする(第5条)。
労働安全衛生法
→事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない(第3条)。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
→パワハラ防止にむけた環境整備、相談者に対する不利益の排除、社内研修などパワハラに関する従業員への周知等
男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」
→セクハラ・マタハラ・ケアハラ防止等に対する体制整備
具体的な事故例4
解雇に納得がいかず従業員が不当解雇を主張し裁判へ。和解金(バックペイ4か月分)+弁護士費用で140万円の損害。
→従業員との雇用契約に基づく義務違反。不当解雇は「債務不履行」の一種と解されます。
具体的な事故例5
採用契約前に本人に賃金や業務内容、採用予定日を伝えたがその後、内定を取り消した。本人からは実質的な雇用契約であるとユニオンを介して損害賠償請求。
→和解金(バックペイ5か月分)115万円+弁護士費用50万円の損害
③使用者賠償責任
従業員や建設業における下請け業者などが業務によって被った怪我や病気によって企業に損害賠償請求してきた際などの補償。
主に企業側に安全配慮義務違反があったと認められた場合に発生する損害リスクです。
治療費・慰謝料(精神的苦痛)・逸失利益が主だった請求ですが、特に逸失利益(将来得られるはずだった給与や収入)はライプニッツ係数と裁判の前例から高額化傾向にあるため、総額での賠償金が1億円を超えるケースが増えています。
該当する法的責任
債務不履行責任(民法415条) 労働契約上の「安全配慮義務」の不履行。労災とは別に民事責任が問われます。
具体的な事故例6
業務中に高所から落下し腰椎損傷、右半身に麻痺が残った。
→治療費120万円・休業補償180万円・逸失利益6200万円・自宅のバリアフリー改造200万円=総額6,700万円の賠償
④役員賠償責任
役員の経営判断ミスによる損害。民法とは別の「経営責任」に関する特別規定が適用されます。
役員が注意義務を怠って会社に損害を与えた場合、会社から個人として賠償請求されることがあります(会社法423条など)
取締役の職務執行に過失があり、第三者に損害を与えた場合、その取締役が直接賠償責任を負うこともあります。(会社法429条など)
「うちは中小企業だから関係ない」と思われがちですが、最近は株主、取引先、元従業員、時に金融機関からも責任追及される事例が増えています。
特に、同族経営やワンマン経営の会社では、「社長個人」が責任を背負う構造になりやすく、備えが必要です。
該当する法的責任
会社法上の役員責任 善管注意義務違反(会社法423条等)、会社法第429条(第三者に対する責任)
具体的な事故例7
M&A後に買収先企業の業績が大幅に悪化し、株主が損害を主張。
→情報開示不足やデューデリジェンス不足を理由に、役員個人に損害賠償請求1,100万円の賠償請求が発生
具体的な事故例8
不正会計が発覚し、監査役が監督責任を問われた。
→内部統制の不備を見逃していたとされ、役員としての注意義務違反として200万円の賠償請求が発生。
⑤サイバー賠償責任
企業サイバー攻撃を受けたことにより、その企業を踏み台として第三者(顧客や取引先)へサイバー攻撃を波及させたことにより第三者に与えた場合の損害賠償の補償などがメインになります。
賠償金額だけでなく、弁護士・専門業者などの対応費用原因調査・復旧のための費用もかさみ、思わぬ財務逼迫リスクをはらんでいます。
近年では風評被害リスクに対して謝罪広告・広報対策費などの企業負担額も増加しています。
該当する法的責任
不法行為責任(709条)または債務不履行責任(415条)
(顧客との関係性により異なる)一般顧客であれば不法行為、既存契約のある顧客に対する漏洩は債務不履行になるケースもあります。
具体的な事故例9
顧客情報の漏洩により、報道・謝罪・補償金・システム改修など2,000万円の損害
5. 契約時の注意点
ではこのように複雑でかつ多種多様な賠償補償をどのように選ぶのが良いでしょうか。選ぶ際のポイントは大きく3つあります。
①リスクのあぶり出し
まず、人・物・資金の観点から自社のリスクをしっかりとあぶり出す。
特に補償の対象範囲:誰が、何に対して、どのような損害を補償したいのかを明確にします。
②保険にリスクを移転するものを選ぶ
次にそのリスクの損害結果の大きさと、発生度合い(起こりやすさ)からリスクを保険に移転するのか、自社でリスクを保有するのか、または企業努力によってリスクを低減させるのかを分類する
③該当保険を選ぶ
最後にそのリスクに該当する保険を保険代理店を選ぶ。
この際に損害保険会社を1社しか取り扱っていない保険代理店を選ぶと実際の自社リスクに対応できる保険商品がない可能性もあるため注意です。
少なくとも2社または3社以上取り扱っている保険代理店を選ぶことで、保険会社毎の補償のばらつきによる自社リスクカバー不足を抑えられます。
また、金融庁が2017年に定める「お客様本位の業務運営に関する原則」に対して取り組み方針を定め、しっかりと金融庁のHPに記載されている保険代理店を選ぶことで、よりよい商品・サービスの提供を受けられます。
近年の災害リスクから中小企業庁が認定する事業継続力強化計画認定制度で認定を受けている保険代理店を選ぶことで、地震や自然大災害時に保険代理店と連絡をとれないといったリスクを軽減することも大切です。
6. 専門代理店としての強み
最後にCREATEでは、①リスクのあぶり出し、②移転するリスクを選ぶといった作業を全てのお客様にしっかりヒアリングをしながらすすめてまいります。
そこから法人の賠償補償に特化した総合保険代理店として、事故発生から対応まで、「正確・最適・安心・あったらいいな」という観点を忘れずにすべての工程に「専門知識」をもったスタッフが対応します。
中小企業の経営者の皆様が本業に集中できるよう、「もしもの賠償リスク」に備えるプロの伴走者でありたいと考えています。
ウェブ面談を申し込む
どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。